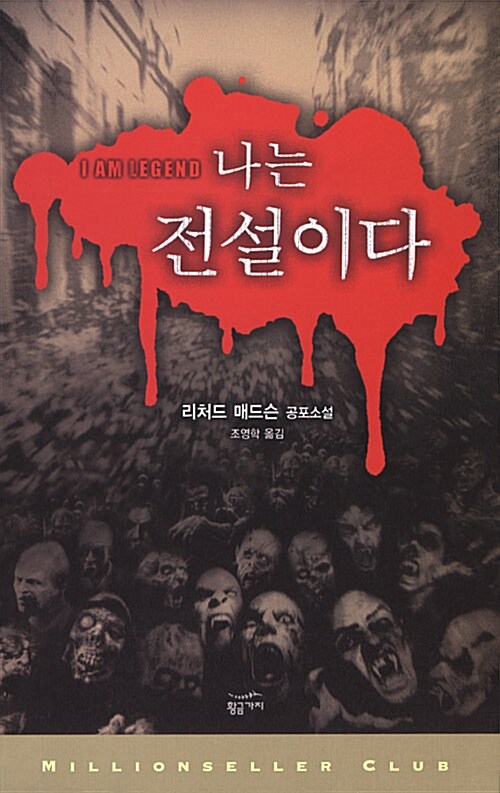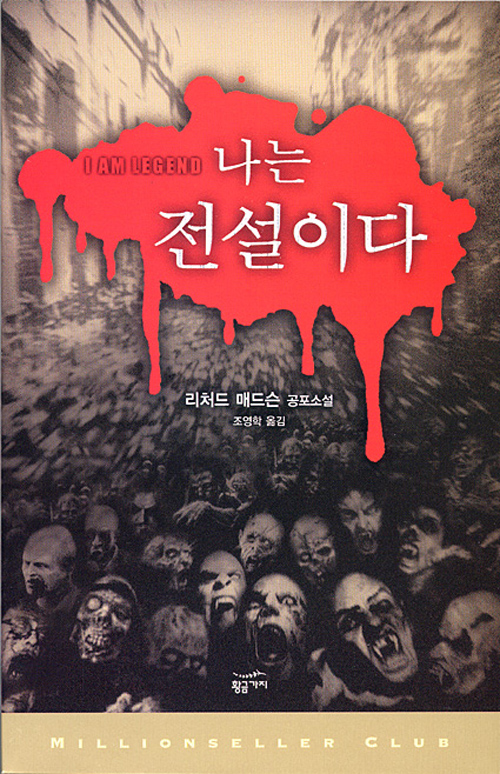リチャード·マッドソン「私は伝説だ」(ネタバレあります。)
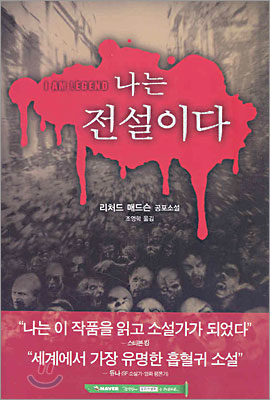
タイトルが「私は伝説だ」だが、この本こそ伝説。ウィル·スミス主演の「私は伝説だ」は以前見たよ、当然。 映画も面白かったし、よくできた作品だと思った。 そこで探してみたこの原作小説は面白いという表現さえ申し訳ない秀作。 その上、当然本も映画のような設定とあらすじだろうと信じて読んだので、この本を読む時間がさらに興味深かった。 本の中の主人公ネヴィルは、映画の中の主人峰ウィル·スミスよりはるかに人間的で孤独で辛い人間だったからだ。 本と映画の違い■本に描かれているゾンビたちは一般的なゾンビ映画で定型化されて現れる(映画「私は伝説だ」も同様)ゾンビたちの形状とは大きく異なる。 ゾンビ特有の血が乾いて歪んだ気持ち悪いことに対してはここでも描写しているが、ほとんどの叙述は彼らが依然として外形的には人間だと言い張っても差し支えないほどの外形は維持していることが明らかになる。 腐ってしまったり、体が壊れてしまったゾンビ以外のほとんどのまともなゾンビは肉眼で人間との識別が難しいほどだ。 この点はこの小説の結末と多大な関連がある。■ 本の主人公ネヴィルは徹底的に一人だ。 セパートの鐘である犬のサムと一緒に歩きながら、お互いに頼り合って守る映画の主人公とは全く違う。 あまりにも寂しくて孤独なので、本の中のネヴィルはゾンビの女性たちを見て性欲を感じたり、そんな自分の存在が呪われて自害したり、アルコールに頼ったりする。 本でもしばらく犬が登場するが、そのさすらいの犬はネヴィルの寂しさを慰めるパートナーというよりは、彼の孤独をより切実に表現する媒介体として現れる。 生きている生命体とは初めてだった放浪犬に出会ってから、彼に完全に捕らえられたネヴィル。 ネヴィルはその犬を手なずけるために危険を冒して長い時間無残に努力するが、辛うじて心を許した犬が彼の胸で息を引き取る場面は、この地獄の中でネヴィルが徹底的に一人だという事実を悟らせてくれる。■ 一番違う点はやはり結末の部分だ。 映画の結末は結局、ウィル·スミスを通じてまだ残っているヒューマニティを力説することで結ばれる。 ウィル·スミスは最後まで偶然会った他の人間母娘を助け、本人が渾身の力を尽くして作ったワクチンを伝達することで人類を救い壮烈に戦死する。(内容が少し違うが、監督版の結末も人間救援を土台にしているという点は同じだ。)しかし小説の中のネヴィルの最後は彼とは違う。 ネヴィルはゾンビと人間の両者の間の性向を全て持つ新しい種族を迎えることになり、本人が生存している最後の人類という事実に気づくことになる。 苦悩していたネヴィルはついに最後のたった一人の人間として自殺を選択しながら「今や私は伝説だ」と宣言する。 小説「私は伝説だ」の力はその優れた描写力にある。 リチャード·マドセンは、ディストピア的な近未来、すなわち世界中が廃墟となり、生存者はおらず、ゾンビだけがうきうきしながら、一時隣人だった者たちが主人公の血を吸うために毎晩家に押し寄せ、窓や壁を叩き、絶えず悲鳴を上げるネヴィルの現実を鳥肌が立つほど生々しく描写する。 また、ネヴィルが住んでいる家の姿も十分に読者の頭の中に刻まれるほど詳しく叙述される。 読者たちはゾンビが現れない昼間の間、彼がニンニクのネックレスや発電機の修理にどれほど気を使っているのか、缶詰がいっぱいの部屋に入るたびにどんな気持ちなのか、どんな気持ちで壊れた窓と壁を補修するのかなどを一緒に苦難を経験する同志のような気持ちで体験することになる。しかし、やはり作家の描写力が最も光を放つ部分は人間ロバート·ネヴィルの心理表現だ。 本の中のネヴィルは、映画でウィル·スミスが演じたように孤独だが、タフでクールで強くて素敵な男ではない。 ネヴィルはアルコール中毒に陥って抜け出すことを繰り返し、よく死んだ妻と娘を考え、このような状況でも性欲から自由ではない自らを呪う人間だ。 さすらい犬を抱いてその体温に感激し果てしない愛を感じながらも、いざ現れた人間(ように見えた)女性には警戒心を緩めることができない。 これらすべてがネヴィルだ。 このネヴィルが考え、動く過程を共に体験できるというのが、この荒唐無稽なSF小説を読みながら心から戦慄し恐れ孤独になれるというのがこの小説「私は伝説だ」が持つ最も美徳だろう。[][][][][][]